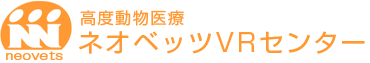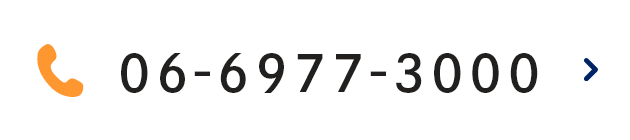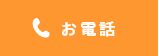ブログ
VNブログ 【大腸内視鏡検査】 2017.2.28
今月のVNブログは吉平動物看護師から
大腸内視鏡検査のお話です。
人間と動物の検査の違いをお伝えします。
 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
こんにちは。動物看護師の吉平です。
先日、私自身が大腸内視鏡の検査を受けてきました
普段、職場で犬や猫の大腸内視鏡検査を見ているなか、
まさか自分が検査される側になるとは思ってもなく、
なかなか貴重な体験でしたので今回のブログでお話
させていただきます
まず、大腸内視鏡検査とは、一言で言うと、
肛門からカメラを入れ大腸内を観察する検査です。
主に大腸内のポリープや腫瘍の有無、炎症の程度などを
観察します。
また、ポリープや腫瘍が見つかった場合は、専用の鉗子で
組織の一部を採取し、病理検査に出したりもできます。
カメラを通し肉眼で状態を見ることができるため、診断が
しやすい検査です。
下痢や便秘、血便、排便時のしぶりなどの症状がみられ
検査を行うことが多いです。
私も健康診断で潜血便が出たのがきっかけで検査を行いました
ここからは、私が受けた検査内容を交え、動物の検査との
違いをご紹介します。
まず、大腸内視鏡検査を行う事前準備として大腸を空にします
大腸に内容物が残っていると、それが邪魔し、しっかりと
観察することができなくなります。これは人も動物も共通です。
そのため、前日からの絶食が必要になります(12時間以上)。
ただ、半日程度の絶食では大腸は空になりませんので、
人では大量の水分と下剤を飲んで大腸を空っぽにします。
私の場合は合計約2リットルの下剤を10分毎くらいに飲みました
では、動物も同じように下剤を飲ませるかというと、おそらく
無理でしょう。大量の下剤を飲ませるのも難しいですし、
何より下剤ですので排泄の処理が大変でしょう


そこで、動物の場合はカメラを挿入前に浣腸をして大腸に
溜まった便をかきだします。
長めのチューブを肛門から挿入し、ぬるま湯を流し込んで、
大腸内を洗浄します。
(場合によっては人でも浣腸といった方法をとる場合もあるそうです。)


しっかりと洗浄を行い、空っぽになると上の写真のようにきれいに観察することが出来ます

次に違いを感じた点としては挿入するカメラの太さです
VRセンターで動物に使用している内視鏡カメラの先端部は
直径5.5ミリメートルのものと8.6ミリメートルのものになりますが、
今回私が検査に使用したものは約14ミリメートルでした
約2倍もの大きいサイズに不安にはなりましたが、特に痛みや
不快感はなく検査は終了しました

 右から5.5ミリ、8.6ミリ、14.0ミリ
右から5.5ミリ、8.6ミリ、14.0ミリ
※14.0ミリは実物がないので代わりのもので比較しています。
更に、人と動物の最大の違いは全身麻酔の有無です。
人の場合は、全身麻酔をかけて検査を行うことは
ほとんどありません。私の場合も軽い鎮静のみでした。
しかし、動物の場合は、不動化のために必ずと言っていいほど
全身麻酔をかけます。
浣腸から検査終了まで麻酔をかけた状態で行うため、検査自体が
大きな痛みとして感じることはありません。
麻酔のリスクを除けば、検査時は動物のほうが快適に行われる
のではないかと思われます。
しかしながら、麻酔の影響はしばらく残ってしまいますので、
日帰り検査ではありますが、検査後はできるだけ安静にさせる
必要はあります


今回、大腸内視鏡検査を受け、改めて検査の有用性を
知るとともに、検査前の大きな不安と言うものを感じました。
終わってみると低侵襲の検査で日常生活への影響も
ほとんどありませんでしたが、検査前はいろいろとネットで
検索してかなり不安でした
VRセンターに来院される動物たちやオーナー様も検査前は
いろいろな不安を抱え来られているのだと再認識できる
よい経験でした。そのような不安を少しでも取り除けるように
接していくことが動物看護師としての役割のひとつなのでしょう。
なお、私の検査結果は大きな問題はありませんでしたのでご心配なく 。。。
。。。
病気のお話シリーズ vol.16 “門脈体循環シャント” 2017.2.23
今回の病気のお話ブログは、総合診療科の望月先生から
『門脈体循環シャント』に関するお話です
VRセンターでCTを撮られる患者様の中で多い症状のひとつです。
 。o○o。.★.。o○o。.☆.。o○o。.★.o○o。.☆.。o○o。.★.。o○o。
。o○o。.★.。o○o。.☆.。o○o。.★.o○o。.☆.。o○o。.★.。o○o。
総合診療科の望月です。
今回は、当センターでも診断、治療する機会が多い
『門脈体循環シャント』という病気について説明させていただきます。
 門脈体循環シャントとは?
門脈体循環シャントとは?
「門脈」とは胃、腸、脾臓、膵臓からの血液を集めて、
肝臓まで運ぶ血管のことです。
門脈を流れる血液には、消化管から吸収された栄養分と
一緒に、色々な毒素(アンモニアなど)が含まれています。
門脈中の毒素は肝臓で解毒されて、きれいになった血液は
全身を巡る流れ、すなわち「体循環」に合流します。
門脈体循環シャントとは、「門脈」と「体循環」をつなぐ異常な
血管(=シャント血管)が存在することで、門脈中の血液が
肝臓を通らずに全身を巡ってしまう病気です。
本来であれば肝臓で解毒される毒素が全身を回ってしまうことで
様々な問題を引き起こします。
また肝臓に届く栄養分が不足してしまい肝臓自体にも悪影響を
与えます。
門脈体循環シャントには、
生まれつきシャント血管が存在するもの(先天性)と、
肝臓の病気などが原因となり、生まれた後にシャント血管が
できてしまうもの(後天性)がありますが、ここでは当センターで
診断、治療する機会が多い先天性の門脈体循環シャントについて
説明させていただきます。
 どんな患者さんが多いの?
どんな患者さんが多いの?
先天性の門脈体循環シャントは、日本では マルチーズ
マルチーズ ヨークシャー・テリア
ヨークシャー・テリア ミニチュア・シュナウザー
ミニチュア・シュナウザー
などの小型のワンちゃんで多くみられます。
またわんちゃんに比べると稀ではありますが、
ネコちゃんでみられることもあります。
 どんな症状が出るの?
どんな症状が出るの?
門脈体循環シャントで特徴的な症状は、
● 痙攣(けいれん)
● ふらつき
● ぼっーとする
● よだれが多い
などの神経症状で、「肝性脳症」と呼ばれています。
これは本来は肝臓で解毒されるはずの門脈中の毒素が、
脳に影響するために起こる症状です。
門脈体循環シャントでは尿酸アンモニウムという種類の結石が
膀胱や腎臓にできやすくなるため、
● 血尿
● 頻尿
● 尿が出づらい
などのおしっこの症状がみられることもあります。
また、何の症状も見られずに、健康診断のために受けた
血液検査やレントゲン検査でこの病気が疑われ、精密検査で
門脈体循環シャントが見つかることもあります。

 門脈体循環シャントの患者さんから摘出した
門脈体循環シャントの患者さんから摘出した
膀胱結石(尿酸アンモニウム)
 どうやって診断するの?
どうやって診断するの?
門脈体循環シャントの患者さんでは、血液検査で
● アルブミン値の低下
● 血液尿素窒素(BUN)の低下
● 血中アンモニア濃度の上昇
などの異常がみられることがあります。
またご飯を食べた後の総胆汁酸値(TBA)がとても高くなっている
場合にもこの病気が疑われます。
腹部超音波検査で異常なシャント血管が見つかる場合もあります。
当センターでは主に全身麻酔下でのCT検査によって
門脈体循環シャントの確定診断を行っています。
血管に造影剤というお薬を入れてCT検査を行うことで異常な
シャント血管を見つけます。
CT検査ではシャント血管の位置や形も分かるため、手術の
計画を立てる時にもとても役立ちます。

 3Dに再構築したCT画像
3Dに再構築したCT画像 どうやって治療するの?
どうやって治療するの?
先天性門脈体循環シャントを治療するためには手術が必要です。
手術を行うまでの間は、症状を抑えるために
● 低タンパク食の給餌
● ラクツロースというシロップの投与
● 抗生剤の投与
● 特別なアミノ酸(BCAA)のサプリメントの投与
などの内科治療が行われます。
 手術の方法には
手術の方法には
● 結紮術
(シャント血管をしばる方法)
● セロハン結紮術
(シャント血管にセロハンを巻き、ゆっくりとシャント血管を閉じる方法)
● アメロイドコンストリクター設置術
(特殊なリングをシャント血管に取り付け、ゆっくりとシャント血管を閉じる方法)
● コイル塞栓術
(血管を通じてシャント血管にコイルと呼ばれる塞栓物を詰める方法)
などがありますが、当センターでは主に治療の確実性が高い
結紮術を行っております。
結紮術では手術でお腹を開け、シャント血管を直接糸で
しばることで治療します。
この手術で気をつけなければいけないことは「門脈高血圧」です。
門脈高血圧とは、門脈体循環シャントのせいで門脈の発達が
悪い場合に、シャント血管を流れていた多くの血液を門脈が
受け入れることができず、門脈がパンパンになってしまう状態です。
シャント血管を完全にしばった時に門脈の血圧が高くなってしまう
場合には、門脈高血圧を防ぐために手術を2回に分けて行い、
1回目の手術ではシャント血管を細くする程度にゆるくしばり、
その後2回目の手術で完全にしばるようにしています。
 手術写真
手術写真
 さいごに
さいごに
門脈体循環シャントは手術により根治できる可能性が高い
病気であり、早期診断、早期治療が重要です。
この病気を疑う症状や血液検査での異常値がみられる
場合には、ホームドクターの先生に是非相談してみて下さい。
読売新聞から献血の取材を受けました 2017.2.21
2/19(日)の読売新聞に動物の献血に関する記事が
掲載されました
昨年からVRセンターも取材を受けており
献血のドナーさん、輸血を受けた患者さん
複数の方にインタビューを行い、記事は作成されました。
献血中の取材風景

取材にご協力いただいたドナーさん、患者さん
ありがとうございました
献血ドナーに関してご興味を持って頂いた方は
ネオベッツVRセンター  06-6977-3000 まで
06-6977-3000 まで
ご連絡ください。
入院患者さん通信~モモちゃんのリハビリ~ 2017.2.15
ある日の入院室に行くと、椎間板ヘルニアで手術をした
ナナちゃんのリハビリタイムに遭遇しました。
人好きな性格のナナちゃんですが、カメラは嫌い なのか…
なのか…
お部屋の隅っこを向いてしまいました
ナナちゃ~ん

そこに動物看護師登場
お部屋の外の滑らないマットの上に移動です

今日は3つのリハビリをがんばります

モモちゃんのリハビリプランはこちら

左右各50回の屈伸運動

後肢でしっかり立てないナナちゃん
立たせてあげて、3~5分間姿勢をキープ

後ろから前に、円を描くように
左右各50回クルクル
すべてのリハビリが終わったら、清々しいこの表情

リハビリは、手術の翌日に痛みがなければ夕方から
スタートします。退院まで上記のリハビリを
毎日、3~4回行います。
自分で後肢が動かせるように改善してきたら、滑らない所で
歩いたり、ご飯で誘導して歩かせたり、リハビリの
メニューも変わっていきます
お家でもリハビリを続けてもらえる様に、面会や退院時に
リハビリの方法をお伝えしています。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ナナちゃんのお部屋もご紹介します

ポイントは床材
お部屋の床には特殊な素材のクッションマットを敷き
その上にペットシーツ、バスタオル、更にペットシーツを
敷いています。
後肢不全麻痺の為、床を柔らかくしています。
バスタオルも柔らかい素材を使っています。
床ずれしないように

ナナちゃんがリハビリ中にお部屋のルームクリーニングも完了
入院中も意外と忙しいナナちゃんでした。
毎日リハビリを頑張り、手術前しっぽを振れなかったナナちゃんも
退院時は飼い主さんに嬉しそうにしっぽを振りながら帰って行きました

お家に帰ってからもリハビリ頑張ってね
入院患者さん通信~ファン君 お気に入りのおもちゃ♪~ 2017.2.12
ある日の院内で、楽しそうなワンちゃんを発見
脾臓の腫瘍で手術をしたフレンチブルドッグのファン君です
動物看護師とお気に入りのおもちゃで遊んでいました。

院内で行き交うスタッフみんなにおもちゃを持って
『遊ぼう~ 』『遊ぼう~
』『遊ぼう~ 』のアピール全開です
』のアピール全開です
おもちゃを運ぶのはお手のもの


遊んでくれる人が見つかったら綱引きタイム


飼い主さんは、面会に行くと帰れるのかな とファン君に
とファン君に
期待をさせてしまうので。。。と来院を控えていました。
その間にすっかりVRセンターに馴染んでみんなの人気者になりました
7日間の入院を頑張り、退院していきました
もちろんよく寝てる時もありました


第8回獣医整形外科シンポジウム 2017.2.8
2/5(日)東京大学で第8回獣医整形外科シンポジウムが
開催されました。
今回は「トイ犬種の橈尺骨骨折に挑む!~プレート固定の最前線~」
の内容で川田センター代長が座長を務めました。
左側が川田センター代長です

非常に多くの先生方が参加されており、会場はこの賑わいでした。
VRセンターも、橈尺骨骨折で来院される患者さんは
整形外科疾患の中で上位を占めています。
トイプードル、チワワ、ポメラニアンなどの小型犬たちを
1m位の高さから落としてしまって骨折した
ソファーやベットから飛び下りて骨折した
などの患者さまが多いです。
VRセンターでは早期に手術を行なえる様努めています。
昨年は、橈骨尺骨骨折の整復手術を56件行いました。
高い所から飛び下りて前肢を挙げていたり、痛そうにしているなどの
症状がある場合は、お早めに主治医さんにご相談下さい
ふーたちゃんのお母さん作。2月バージョン ♪ 2017.2.6
先日立春を迎えましたが、春はまだまだ先だな・・・・
と感じる寒い毎日ですね。
そんな中、今月もふーたちゃんのお母さんから
カレンダーが届きました~
かわいいふたりの姿に心がほんわか温まりました。
ひと足お先に心に春を運んでくれました

カレンダーのふーたちゃん&そーたちゃんは
マフラー姿でまだまだ防寒対策中ですが・・・


そして今月のポストカードはこちら


絶妙な愛くるしい瞬間の表情をバッチリ捉えているお母さん

お母さんとふーたちゃんの意気のあった1枚を楽しませてもらいました。
献血のドナー登録ありがとうございます 2017.2.1
先日、同居犬の手術の為に献血をしてくれたワンちゃんが
今後も献血にご協力頂けるとのことでドナー登録を
してくれました

 佐藤ぶんた君 1才 アメリカンピットブル
佐藤ぶんた君 1才 アメリカンピットブル

 内芝リディアちゃん 1才 ジャーマンシェパード
内芝リディアちゃん 1才 ジャーマンシェパード
昨年、ドナーのワンちゃんが2頭卒業した為、今回
若いブンタ君とリディアちゃんが新しくドナーとなって
いただきとても助かります
現在、ドナー登録頂いているワンちゃんは20頭です。
たくさんいる様にも感じますが、献血が必要な患者さまが
重なると決して多くはない状態です。
今後もドナー登録して頂けるワンちゃんをお待ちしております
“子猫リレー事業” ご存知ですか? 2017.1.26
2015年から大阪でスタートした「子猫リレー事業」をご存知ですか
飼い主のいない子猫たちの命をつなぐ新しい取り組みです。
簡単にお伝えすると・・・
 保護されてから、3ヵ月齢まで
保護されてから、3ヵ月齢まで
(公社)大阪市獣医師会の会員動物病院で過ごします
ワクチン接種などのメディカルケア、食事やトイレの
しつけが行われます。
 3ヵ月齢~6ヵ月齢まで
3ヵ月齢~6ヵ月齢まで
キトンシッターボランティアさんの元で過ごします
原則60才以上の方のお家で、人が大好きなネコちゃんに
なれるように3ヵ月過ごします。
 そして、いよいよ一生を共にするお家へ
そして、いよいよ一生を共にするお家へ
この子猫リレー事業で育ったネコちゃんを家族に迎えたのが
当院の中山動物看護師
相棒となったのは、やんちゃなくらい元気いっぱいの
マタタちゃんです


先日、子猫リレー事業に関する取材も受けました
画像をクリックして頂くと大きな画像になります


里親となった経験談をお伝えするシンポジウムにも参加します
生の声を聞いてみたい方は是非ご参加下さい
日時:平成29年2月12日(日) 14時半~16時半
場所:新日本カレンダー㈱ 3FNKホール
※VRセンター横の建物です
内容:こんなに楽しい子育て奮闘記
ワンちゃんもご一緒に参加していただけます

詳細は下記をクリックしてください
★☆詳細ご案内&お申込み用紙☆★
子猫リレー事業の詳しいパンフレットはVRセンターの
待合にも置いています 宜しければお持ち帰り下さい。
宜しければお持ち帰り下さい。

エイト君、献血 ご協力ありがとうございました 2017.1.24
先日、献血に協力してくれたエイト君
今回も急なお願いとなったのですが、お願いのご連絡から
30分程で駆けつけてきてくれました。
手術後の患者様に輸血させていただきました。
節分が近いので、今回は節分バージョンで
節分といえば、豆まきと恵方巻
今年の恵方巻の方角は北北西。
願い事をしながらもくもくと食べて福を呼び込みましょうね
ワンちゃんネコちゃんの健康も願いつつ・・・・


ご協力ありがとうございました