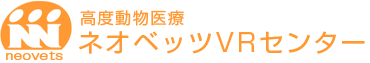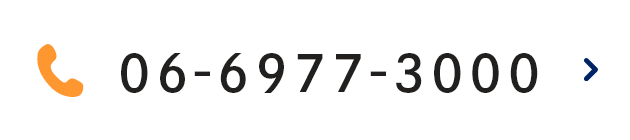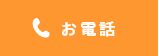ブログ
病気のお話シリーズ vol.15 “異所性尿管” 2017.1.19
今回の病気のお話ブログは、総合診療科の森下先生から
『異所性尿管』に関するお話です
後半、手術中の動画が含まれています

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
総合診療科の森下です。
今回は『異所性尿管』という病気を紹介させていただきます。
 異所性尿管とは?
異所性尿管とは?
若い女の子のわんちゃんでよくおもらしをする、
それはもしかしたら異所性尿管かもしれません。
比較的「まれ」な病気ではあるものの、雄よりも雌で
臨床症状を示すものが多い、猫より犬で多いというのは
知っていただいていてもいいかもしれません。
ややこしい説明になりますがご説明させていただきますと、
尿管とは腎臓と膀胱をつなぐ管です。
尿は腎臓で作られ、尿管を通って膀胱まで運ばれます。
膀胱は尿をためておく袋状の構造物であり、
さらにその袋からペニス、あるいは膣につながる管、「尿道」が
存在します。
膀胱~尿道の間には括約筋という尿道の周りを囲むような
筋肉があります。
この筋肉が尿道を「きゅっ」と締め付けることによりいわゆる
「おしっこのがまん」ができるのです。
尿管は本来イラストでお示しした膀胱の後ろのほう(膀胱三角)に
開口するのですが、膀胱でないところに開口してしまうと、
尿が持続的に流れでてしまい「お漏らし」という形で人間の目に
映ることがあります。
これが異所性尿管で尿失禁がでるメカニズムになります。


 飼い主さんから見て気づく兆候
飼い主さんから見て気づく兆候
排尿姿勢をとらない尿失禁をする、という症状で
気づかれることが多いです。
元気食欲に問題があることはほとんどありません。
 診断・治療
診断・治療
経過などから本疾患を疑った場合は、尿管の通常と
異なる位置での開口を見つけることが診断になります。
尿管はとても細いために当院では造影剤とCT検査を
組み合わせた排泄性病路造影を行い診断、および
手術計画を立て、顕微鏡下で正常な場所への尿管
開口部の移設手術を行っております。
“左側の壁内性異所性尿管”を診断した際の画像検査です。
オレンジの矢印が
膀胱を超えて伸びている解剖学的に異常とされる「異所性尿管」です。



当院副センター長、宇根による手術の様子をご覧ください
「動画」:約2分 下記画像をクリックしてください


 最後に
最後に
異所性尿管は致命的な疾患ではないですが、持続的な
尿失禁の改善にて生活の質の向上が期待できるため、
持続的に尿疾患があるなど、気になることがあれば
一度検査を受けていただき、外科治療の可能性を模索
させていただけたらと考えております。
病気のお話シリーズ vol.15 “異所性尿管” 2017.1.19
今回の病気のお話ブログは、総合診療科の森下先生から
『異所性尿管』に関するお話です
後半、手術中の動画が含まれています

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
総合診療科の森下です。
今回は『異所性尿管』という病気を紹介させていただきます。
 異所性尿管とは?
異所性尿管とは?
若い女の子のわんちゃんでよくおもらしをする、
それはもしかしたら異所性尿管かもしれません。
比較的「まれ」な病気ではあるものの、雄よりも雌で
臨床症状を示すものが多い、猫より犬で多いというのは
知っていただいていてもいいかもしれません。
ややこしい説明になりますがご説明させていただきますと、
尿管とは腎臓と膀胱をつなぐ管です。
尿は腎臓で作られ、尿管を通って膀胱まで運ばれます。
膀胱は尿をためておく袋状の構造物であり、
さらにその袋からペニス、あるいは膣につながる管、「尿道」が
存在します。
膀胱~尿道の間には括約筋という尿道の周りを囲むような
筋肉があります。
この筋肉が尿道を「きゅっ」と締め付けることによりいわゆる
「おしっこのがまん」ができるのです。
尿管は本来イラストでお示しした膀胱の後ろのほう(膀胱三角)に
開口するのですが、膀胱でないところに開口してしまうと、
尿が持続的に流れでてしまい「お漏らし」という形で人間の目に
映ることがあります。
これが異所性尿管で尿失禁がでるメカニズムになります。


 飼い主さんから見て気づく兆候
飼い主さんから見て気づく兆候
排尿姿勢をとらない尿失禁をする、という症状で
気づかれることが多いです。
元気食欲に問題があることはほとんどありません。
 診断・治療
診断・治療
経過などから本疾患を疑った場合は、尿管の通常と
異なる位置での開口を見つけることが診断になります。
尿管はとても細いために当院では造影剤とCT検査を
組み合わせた排泄性病路造影を行い診断、および
手術計画を立て、顕微鏡下で正常な場所への尿管
開口部の移設手術を行っております。
“左側の壁内性異所性尿管”を診断した際の画像検査です。
オレンジの矢印が
膀胱を超えて伸びている解剖学的に異常とされる「異所性尿管」です。



当院副センター長、宇根による手術の様子をご覧ください
「動画」:約2分 下記画像をクリックしてください


 最後に
最後に
異所性尿管は致命的な疾患ではないですが、持続的な
尿失禁の改善にて生活の質の向上が期待できるため、
持続的に尿疾患があるなど、気になることがあれば
一度検査を受けていただき、外科治療の可能性を模索
させていただけたらと考えております。
VNブログ 【家族動物紹介】 2017.1.12
今月のVNブログは福嶌動物看護師が、我が家の
猫たちを紹介します。

 ————————————————-
————————————————-


皆さん、こんにちは。
動物看護師の福嶌歩です。
新しい年を迎え、いかがお過ごしでしょうか。
我が家は昨年5月から新たな家族動物を迎え、一段と賑やかになりました
という事で
今回のブログは、我が家の家族動物紹介をしたいと思います。
 まずは一頭目
まずは一頭目 

名前:雪虎(せつこ)
種類:Mix
年齢:7歳
性別:♀
性格:マイペース
特技:錠剤の薬をそのままおやつのように食べること
猫じゃらしをよだれでべちょべちょにすること
とても大人しく、同伴出勤する際にいつも更衣室内をウロウロ
歩き回ったり、食事も掃除機のように吸い込んで食べるため、
よくスタッフから『猫じゃないみたい!』と言われます
実は、度々ネオベッツBLOGにも登場しています
 続いて、二頭目
続いて、二頭目

名前:きじっこ
種類:Mix
年齢:6歳
性別:♂
性格:野性的
特技:縦ニャンモナイト( :左上)になること
:左上)になること
犬用のおもちゃを破壊すること
とにかく野性的で、過去に私の部屋の網戸を開けてベランダに
出て隣の部屋の網戸を開けて戻ってくるというミラクルな事件を
起こしました (よい子は真似しないで下さい・・・
(よい子は真似しないで下さい・・・ )
)
最近は徐々に落ち着いてきていますが、相変わらず猫用の
おもちゃはすぐに破壊してしまうので、犬用のおもちゃでしか
遊べません
それでもしばらくすると破壊されていますが・・・。
そして最後に・・・ 昨年5月にやってきた三頭目
昨年5月にやってきた三頭目

名前:八兵衛(はちべえ)
種類:Mix
年齢:9ヶ月
性別:♂
性格:やんちゃ、自由奔放
特技:ミニトマトのヘタを咥えて走り去ること
食器をひっくり返して遊ぶこと
とにかくやんちゃです。
全ての物事に興味津々で、毎日楽しそうに全力で暴れ回っています
お留守番の後はしばらく引っ付き虫でゴロゴロスリスリ・・・と、
実は寂しがりやな一面もあります
以上の3頭が、我が家の家族動物です


みんなそれぞれ性格が異なりますが、それぞれの可愛さに毎日癒やされ、
たくさんのパワーをもらっています。
どれだけ疲れて帰っても、この子たちの顔を見れば疲れなんて吹っ飛びます。
私も皆さんと同じように、飼い主の一人です。
飼い主にとって、家族動物はかけがえのない唯一無二の存在だと思います。
私たちは、毎日その大切な命を預かっています。
私自身が飼い主であり、動物看護師でもあるからこそ、VRセンターに
来院される飼い主様と患者さん(動物)の心に寄り添う看護を提供したい。
そう思うのです。
皆さんに『満足した看護が受けられた』『VRセンターに来て良かった』と
思っていただけるよう、これからも頑張っていきたいと思いますので、
どうぞ宜しくお願い致します。
今年も皆さんと動物たちが、共に幸せな時間を過ごせますように…

ふーたちゃんのお母さん作。1月バージョン ♪ 2017.1.8
今月もふーたちゃんのお母さんがカレンダーを送ってくれました
おめでたい雰囲気溢れるお正月バージョンでした。

そして今月のポストカードはこちら


色違いの羽織がとってもお似合い

ペアールックでかわいらしさ倍増です
兄弟犬で飼っている特権だなぁ。。。。
ふーたちゃん&そーたちゃん新年のご挨拶ありがとうございます。
今年もお母さんのモデル犬として大活躍してね
2017年 新年のご挨拶 2017.1.4
明けましておめでとうございます
年末年始ゆっくりしたスタッフ、VRセンターで入院患者さんたちと
新年を迎えたスタッフ、様々ですが、今日からはいつもの活気に
満ちたVRセンターが戻ってきました

2017年もスタッフ一同、患者様に寄り添った診療を行って参ります。
心配事がございましたらお気軽にお尋ねください

2016年 年末のご挨拶 2016.12.30
今年も残すところ2日となりましたね。
先日から急に寒さが増し、冷たい風が身にしみますね

さて、2016年のVRセンターと言えば
やはり320列の最新鋭CT装置が入ったことが
1番のニュースでした
無麻酔CTを希望される患者様も増えております。
すべての患者様に無麻酔CTが可能ではありませんが
条件次第で無麻酔CTの撮影も行っています。
その他にも撮影時間が短縮されたりと高性能ぶりを
発揮しております。
来年はどんな年になるのか
また、様々なVRセンターの出来事をブログで
お伝えしたいと思います。
来年もオーナー様、患者様にご満足頂けるホスピタリティーを
提供できる様、スタッフ一同努めて参りたいと思っています。
VRセンターの入口はすっかり新年を迎える準備が整いました。

では、最近スタッフのお家に来た3ヵ月の小春ちゃんから・・・


VNブログ 【入院室のぬいぐるみ達】 2016.12.21
今月のVNブログは山田動物看護師が入院室で患者さんに
寄り添う癒し系スタッフをご紹介します。
かわいい写真にほっこりしますよ

 。。^^^^^^^^。。^^^^^^^^。。^^^^^^^^。。^^^^^^^^。。^^^^^^^^。。
。。^^^^^^^^。。^^^^^^^^。。^^^^^^^^。。^^^^^^^^。。^^^^^^^^。。
こんにちは
動物看護師の山田です。
今回は、当院で活躍している癒しのぬいぐるみ達についてご紹介します
の前に・・・
皆さんは、ぬいぐるみセラピーというものをご存知ですか
人間のセラピーでは、ぬいぐるみと一緒に寝ることで
不安やストレスを解消する効果があると言われているそうです

人で効果があるなら動物にもぬいぐるみセラピーが応用
できるのではないか
 と思い、家にあったぬいぐるみを
と思い、家にあったぬいぐるみを
持ってきたのが、入院室の癒しのぬいぐるみ誕生の
きっかけでした
では、ご紹介します
この子達が当院の癒し系担当ちゃん達です

青色の猫ちゃんが私の持参した、ぬいぐるみです
現在は、飼い主様からいただいた犬のぬいぐるみや
他のスタッフが持ってきたキリンのぬいぐるみも
当院で活躍しています。
実際ケージ内にぬいぐるみを入れた時の写真です
 あんじゅちゃん
あんじゅちゃん 
甘えん坊のあんじゅちゃんは、ケージに入ると
分離不安が強くなる傾向にありましたが、ぬいぐるみを
入れてからは、分離不安も落ち着き、ぬいぐるみを
枕にしたり添い寝したりしてリラックスしてくれました。
これをきっかけに退院後、お母さんに大きいスヌーピーの
ぬいぐるみを買ってもらったそうです


 まめ太くん
まめ太くん 
とても怖がりさんのまめ太くんは、入院当初はかなり
緊張していましたが、ケージにぬいぐるみを入れると
緊張がほぐれたのか、スタッフにも甘える様になって
くれました


 ナイトくん
ナイトくん 
同居犬がたくさんいるナイトくんは、一人のケージは、
なかなか慣れず、寝付けない様子でしたがぬいぐるみを
入れると夜は安心したのか、ぐっすり眠れていました


 天くん
天くん 
ケージの扉をカリカリして外に出たがる天くんでしたが、
ぬいぐるみを入れてからは、猫のぬいぐるみに手を添えたり、
寄り添ったりしてリラックスし、ケージの内の環境にも
慣れるようになりました。夜もぬいぐるみと添い寝でぐっすり
休めていました



患者さんの性格や状態によっては、向き不向きはありましたが、
ぬいぐるみをケージ内にいれることでリラックスできている
患者さんはたくさんいました
みんな可愛いくて、ついつい写真を撮ってしまいました


そして、患者さんの可愛いさに私も癒されてしまいました 

今後もより良い看護を追求していく為に、色々なことをとり入れて
いければと思っております。
何かあればいつでもお声かけ下さい
アンジュちゃん、献血 ご協力ありがとうございました 2016.12.19
先日、献血に協力してくれたアンジュちゃん
夜の遅いお時間でしたが、ご来院いただきとても助かりました。
いよいよ今週はクリスマス

前回のベルン君に続き
アンジュちゃんもクリスマスバージョンで

ご協力ありがとうございました
病気のお話シリーズ vol.14 “犬の前十字靭帯断裂 パート3” 2016.12.15
今回の病気のお話しブログは、整形外科の戸次先生から
『犬の前十字靭帯断裂 パート3』に関するお話しです
今迄の“パート1”と”パート2”も文字の上をクリックすると
ご覧いただけます


 ^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^
^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^。^![]()

ネオベッツVRセンター整形外科の戸次です。
今回の“病気のお話”は、『犬の前十字靭帯断裂 パート3』です。
前回までは、初診時に実施する整形外科的検査(視診、触診)
そしてX線検査(レントゲン)といった無麻酔で実施可能な検査に
ついてお話ししました。
今回は、そこから一歩踏み込んだ麻酔下検査として、関節鏡検査と
CT検査についてお話しします。
(麻酔をかける前には、ホームドクターもしくはVRセンターで
血液検査を行い、麻酔をかけても問題ないかどうかを確認する
必要があります。)
関節鏡検査は、直径1.9〜2.3mmのスコープ(動物の大きさにより選択)を
関節内に挿入し観察するという検査であり、前十字靭帯断裂の仮診断が
下された動物に対して、基本的にルーチンで行っています。
 利点
利点
・関節内構造部を拡大観察できること
・前十字靭帯の変性や部分断裂といった初期病変も把握し
確定診断が可能なこと
・低侵襲で術後の回復が早いこと
 欠点
欠点
・関節外(骨、筋肉、関節包の外側)や膝関節尾側の観察が困難なこと
・技術習得まで時間がかかること、高額機器など 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
※実際の関節鏡検査の流れを解説していきます
 麻酔をかけた後に股関節から足先までの
麻酔をかけた後に股関節から足先までの
毛刈り及び消毒を行います

 次に手術台に保定し、滅菌ドレープで
次に手術台に保定し、滅菌ドレープで
手術部位以外を全て覆います
皮膚からの細菌が手指や器具に付着し、術野が汚染されないよう
プラスチックドレープというラップのようなものを皮膚に貼り付けます。
下の写真、赤点線で囲んでいるところに貼っています。

 排泄ポート、カメラポート、器具ポートを作成し、
排泄ポート、カメラポート、器具ポートを作成し、
関節内の観察そして半月板損傷があれば
治療を行います
 語句説明
語句説明 
 排水ポート
排水ポート
関節鏡検査中は、関節内には還流液を常に流し関節内を
洗浄しながら視野の確保を行います。
その時の汚れた液体を排泄するための部位を表します。
 カメラポート
カメラポート
術者の目の代わりとなる、小さなカメラを入れる部位を表します。
 器具ポート
器具ポート
術者の手の代わりとなる器具を入れる部位を表します

 関節鏡所見①
関節鏡所見①
滑車溝に発生した骨棘(こっきょく)
(骨の一部が骨端部付近で棘状に突出しています)

 関節鏡所見②
関節鏡所見②
損傷していない十字靭帯(画面は後十字靭帯)は、
張りがあり、キラキラと輝いている

 関節鏡所見③
関節鏡所見③
断裂した前十字靭帯

 関節鏡所見④
関節鏡所見④
内側半月板をプローブという器具で触知し、
損傷の有無を調べている

 関節鏡所見⑤
関節鏡所見⑤
内側半月板の後角が損傷し、頭側に逸脱している
下の写真は、上の写真の損傷箇所を囲っています

 術者、助手、機械出し、外回り、麻酔係が
術者、助手、機械出し、外回り、麻酔係が
各自の役割を行い、短時間で正確な手術を
実施するよう努めます
関節鏡検査にかかる時間は、動物の大きさや関節内の状態により
変わりますが、おおよそ10~35分となります
“検査”と名前は付いていますが、ご覧の通り関節鏡検査は
“手術”であり、通常は、関節鏡検査直後に膝関節を安定化する
手術も同時に実施していきます。
(こちらは、パート4でお話しします)
CT検査は、前十字靭帯断裂の検査として、ルーチンに行っている
検査ではありませんが、整形外科的検査やX線検査で腫瘍を疑う
所見があった場合には、必須検査となります。
特に、腫瘍が多い犬種や前十字靭帯疾患にかかりにくい犬種が、
後肢跛行を主訴に来院し、膝関節に病変があった場合は、
注意が必要です。
なぜなら腫瘍性疾患の治療方法や予後は、単なる前十字靭帯断裂と
全く異なるためです。
 左:レントゲン 右:CT検査で骨断面を観察すると
左:レントゲン 右:CT検査で骨断面を観察すると
骨融解が生じていることがわかる(赤点線で囲んだ領域)

 左:正常な右後肢
左:正常な右後肢
右:膝関節周囲に腫瘍がはびこっていることがわかる
CT検査の特徴は、X線を用いて構造物を断面状に観察することが
可能なため、関節鏡検査では観察できない、関節周囲組織や
骨断面の観察に適しています。
CT検査で腫瘍であることが分かれば、整形外科から腫瘍科へ
バトンタッチし、治療を行ないます。
次回パート4では、前十字靭帯断裂に対する治療について
解説していこうと思っております
ネコちゃんにも優しい病院を目指して・・・ 2016.12.8
最近、猫ちゃんブームですよね

テレビでもよく取り上げられていたり
かわいいネコグッズもたくさんありますね
VRセンターも、猫ちゃんの来院が増えたな・・・・と感じます。
そこでネコちゃんに優しい病院を目指し、待合に取り入れたことを
紹介したいと思います。
 待合のイスの配置換えをしました
待合のイスの配置換えをしました

左端に落ち着けるスペースを設けてみました
窓側に回っていただくと・・・・・・こんな感じです
怖がり猫ちゃんは、病院に来ているだけでドキドキしています

更に人の動きやワンちゃんの気配を感じると、ドキドキ度は120%です


そんな猫ちゃんに、こちらのスペースはいかがですか
イスの前を限られたスペースにしました。
人やワンちゃんの行き来がない為、少しは落ち着けるのではないかな と
と
思っています。
また、ワンちゃんの面会時も過ごしやすいスペースになっています

面会中、飼い主さんと一緒に過すご飯タイムも、ゆっくりして
いただけると思います

 怖がり猫ちゃんのキャリーにかけるバスタオルを
怖がり猫ちゃんのキャリーにかけるバスタオルを
待合の棚に設置しました。
VRセンターでは、オーナー様にタオルを提供していただいています
入院室など様々なところで使用させてもらっています。
使用済みのお家で要らなくなったタオルで構いませんと
お伝えしていますが、中にはきれいなタオルを
お持ちいただく方もいます

今回、オーナー様からいただいたタオルに猫ちゃんの
アップリケを付け、怖がり猫ちゃん用タオルをご用意しました。
怖がり猫ちゃんは、ワンちゃんにキャリーを覗き込まれることでも
ドキドキ度120%になります


待合でお待ちの間、キャリーにかけてあげてください。
周りの雑踏が軽減され、きっと少し安心できるはずです

少しでもネコちゃんの緊張が和らぐ病院となる様に・・・・
もちろんワンちゃんにも快適に過ごしてもらえるといいな・・・・と願って