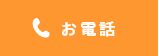ブログ
ビー・ブラウン エースクラップ様 VRセンター見学 2016.4.13
先日、ビー・ブラウン エースクラップ株式会社の
執行役員 リチャード シル様がVRセンターの見学に
来られました
川田センター代表と

ビー・ブラウン エースクラップ株式会社様は
ドイツに本社のあるビー・ブラウングループの
日本法人として設立された会社です。
ビー・ブラウン本社は創業1839年の医療機器の会社で
世界64カ国に子会社があるグローバルな会社です
この度、VRセンターに隣接している株式会社ペピイ様が
ビー・ブラウン エースクラップ株式会社様の手術器具を
取り扱うこととなり、VRセンターがセット内容に関して
一部助言させていただきました。
そして今回、VRセンターの手術中の様子をご覧になられ
様々な手術器具の使用状況を見学されました。
手術室の様子です


外科手術を多数おこなっているVRセンターからの発信が
様々な動物病院の手術現場でお役に立てれば幸いです。
志儀アンジュちゃん、献血 ご協力ありがとうございました 2016.4.10
4/10(日)志儀アンジュちゃんに献血にご協力していただきました
ご来院時は、とっても元気



チャキチャキの女の子かと思いきや・・・
献血中はとてもお利口さん
じーっとしてくれていたので、あっという間に献血は終了しました。
先生と動物看護師の間で


もう1枚


ご協力ありがとうございました
2016年度新スタッフ紹介 2016.4.5
4/1(金)VRセンターも新しい仲間が加わりました
今年は5名の動物看護師が入社しました。

ひと言インタビューと共に紹介します

目指している動物看護師像を答えてもらいました。
 崎浜 動物看護師
崎浜 動物看護師
診察に来られるオーナー様、動物たちの不安を少しでも
和らげる雰囲気作りや、入院動物たちのストレスをなくせる
工夫ができる様な、責任感のある動物看護師を目指します。
 真栄田 動物看護師
真栄田 動物看護師
明るく元気に、常に笑顔で飼い主様に寄り添える動物看護師を
目指します。
 中山 動物看護師
中山 動物看護師
丁寧な仕事をし、オーナー様や動物たちに少しでも安心感を
与えられる様な動物看護師を目指します。
 柏 動物看護師
柏 動物看護師
向上心を忘れず、患者動物たちの命と真剣に向き合い
信頼できる動物看護師を目指します。
 坊山 動物看護師
坊山 動物看護師
私は、言葉を喋らない患者さんであっても、患者さんの気持ちを
常に考えて、少しでも不安を軽減できるような動物看護師を
目指します。また、飼い主様からも信頼して頂ける動物看護師を
目指します。
今年は女性5名が加わり、院内が更に華やかになったような気がします
 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
夜は、スタッフが集まり新入社員歓迎会を行ないました。
今年は、大阪以外からの新入社員が多かったので
大阪らしく、粉もん歓迎会となりました

お好み焼き、たこ焼き、焼きそばとソース三昧で会場は
とてもいい香りに包まれていました
そして恒例となってきた、VRセンター音楽部
部員は未だ増えずで、田戸先生と森下先生2人ですが・・・
今回は、情熱大陸のテーマ曲を演奏しました
冒頭少しご紹介します
こちらの写真をクリックしてみてください

すべてのスタッフはそろっていませんが・・・・
最後にみんなで、ハイ パシャリ
パシャリ

病気のお話シリーズ vol.11 “角膜潰瘍” 2016.3.30
今月の病気のお話ブログは、眼科の小山先生から
『角膜潰瘍』に関するお話です
この後、角膜潰瘍の痛々しい眼の写真がたくさんあります

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


今回は眼科の担当です。
白内障、緑内障に引き続き、角膜潰瘍(角膜の傷)について
お話したいと思います。
病気のお話をする前に、角膜についての基本的な話をしたいと思います
角膜は眼球の前面に位置し、映像を網膜に届けるために透明性であり
眼球内容物を守る強い膜として存在しています。
そのために角膜は約0.5mmという薄い膜であるにもかかわらず強度があり
コラーゲン線維がきれいに密に並んでいる構造をしています。
角膜は表面から上皮、実質(コラーゲン線維)、デスメ膜、内皮の四層から
なっています。

眼の疾患の中でも角膜潰瘍はよく見られる疾患です。
一概に潰瘍と言っても、その程度は様々で、
![]() 軽いものから、上記の上皮(一番上の層)までの潰瘍を
軽いものから、上記の上皮(一番上の層)までの潰瘍を
『表層性潰瘍』
 実質まで到達した潰瘍を
実質まで到達した潰瘍を
『中層性~深層性潰瘍』
 デスメ膜まで到達した潰瘍を
デスメ膜まで到達した潰瘍を
『デスメ膜瘤』
 角膜に穴があいた状態を
角膜に穴があいた状態を
『角膜穿孔』といい、視覚を喪失する可能性がある
重篤な状態です

それとは別に、 角膜のコラーゲン線維が融解した(溶けた)状態の潰瘍を
角膜のコラーゲン線維が融解した(溶けた)状態の潰瘍を
『融解性潰瘍』と言います。
どの潰瘍も痛みや充血、眼脂が認められ、治療が必要な状態です
しかしながら特に危険な状態は、既に角膜に穴があいている状態の
角膜穿孔、穿孔する危険があるデスメ膜瘤、進行が早い融解性潰瘍です
それ以外には見た目的には重篤な潰瘍に見えなくても、 数週間から数ヶ月間治らない
数週間から数ヶ月間治らない
『自然発生性慢性角膜上皮欠損(SCCEDs)』などがあります。

 /////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////

『角膜穿孔』
角膜に穴があいている状態ですので、眼球内にあるもの
(主には前房水と言われる眼の中の液体)が眼の外に
出て来ます。
液体だけでなく、虹彩(瞳を形づくる茶色い膜)や中には
水晶体などが出てくることもあります。
眼の中の構造物が出てくることはもちろん大変なことですが
液体だけでも出て来た場合には、眼球が虚脱し、眼内出血や
網膜剥離、将来的に緑内障を引き起こし、失明にいたることも
あります。
出来るだけ速やかに、穴を塞ぐ手術が必要になります。
(もしくは自然に穴が塞がるのを待ちます。)
『デスメ膜瘤』
角膜潰瘍が深くなり、内側の薄い膜しか残っていない状態です。
何時なんどき角膜に穴が開いてもおかしくない状態です。
角膜穿孔した場合には、失明の危険が高まるため、安静にして
出来るだけ穿孔する前に潰瘍を修復することをお勧めします。
『融解性潰瘍』

細菌感染やその他の要因で、角膜のコラーゲン線維を
溶かす酵素が働き、固い角膜を柔らかく消化し、溶かして
いく状態です。
進行が早いことが特徴で、半日で角膜が真っ白に混濁し
柔らかくぶよぶよした状態になることもあります。
特にシーズーやパグ、ペキニーズなどの短頭種は融解性
潰瘍を起こしやすいので要注意です。
酵素の働きを止め角膜の融解を止めないと角膜が穿孔する
ことにもなりかねません。
『SCCEDs(別名:難治性角膜びらん、無痛性潰瘍)』
角膜の表面の上皮が剥離した状態で、表層性潰瘍に
分類されます。
通常、表層性潰瘍は1−2週間で治癒するはずですが
いつまでも良くも悪くもならない潰瘍です。
この場合点眼だけではよくならないので、角膜表面の
外科的処置が必要になります。

 ///////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

 治療
治療
角膜潰瘍の治療には、原則、点眼が必須です。
角膜には血管が存在しませんので、飲み薬では十分に
必要な薬を届けることが出来ません。
そのため直接的に薬を届けることが出来る点眼薬が
必要になります。言い換えれば点眼できなければ治療が
不十分となります。
また点眼だけでは対応できないような状況(角膜穿孔や
デスメ膜瘤、SCCEDs)などの場合は手術や処置が必要となります。
 角膜穿孔の手術前
角膜穿孔の手術前  結膜をつかって角膜の穴を塞ぐ
結膜をつかって角膜の穴を塞ぐ
手術後2ヶ月目

反対に、手術で対応できないような状態(角膜全体の融解など)では
点眼治療が重要な役割を発揮することもあります。
また眼を掻くことにより悪化する場合には保護のためエリザベスカラーを
つけてもらう必要があります。
個々の原因や症例、経過などにより治療方法は様々ですので
しっかりとした眼科検査を受けてください。
角膜潰瘍は眼科の疾患の中でも、よく遭遇し、オーナー様でも
見つけやすい疾患です。
早めに見つけて、早めに病院を受診するようにしてください

つね日頃から眼を見る習慣と点眼できるようになっておくことが
望ましいでしょう

VNブログ 【抗がん剤治療中の愛ちゃん】 2016.3.24
今月のVNブログは大森動物看護師から
リンパ腫の治療を行なっている愛ちゃんのお話です。
とてもかわいい愛ちゃんの写真も必見です

 ・・・・・・・・
・・・・・・・・
 ・・・・・・・
・・・・・・・
 ・・・・・・・
・・・・・・・![]()
 ・・・・・・・
・・・・・・・

こんにちは 動物看護師の大森はるひです。
動物看護師の大森はるひです。
VRセンターで働いて早いもので3年目になりました
私は専門学校を卒業後、一次診療と二次診療を行っている病院で
約4年働き、二次診療を専門で行う施設で働きたいと思い今に至ります。
当センターは、整形・神経・腫瘍・眼科・総合診療と科に分かれており
それぞれの科に特化した先生達が診療にあたっています
様々な診察などに携わらせてもらう中で、腫瘍科へ興味を
持つようになりました。
一口に腫瘍といっても様々な種類や治療法があり、その子
その子の状態に合わせた闘い方があります。
手術では根治できないものや、長期の内科治療が必要な
場合など、中には再発の恐れがあるものもあります。
当院では、主治医さんと連携して、手術後も経過を診させて
いただくことや抗がん剤治療を行うケースもあります。

この写真のわんちゃんは現在6歳 ゴールデンレトリーバーの愛ちゃんです

愛ちゃんは、約1年前から当院でリンパ腫の治療を行っています。
抗がん剤治療をはじめとした内科治療で癌と闘っています
血液検査や、時にはレントゲン検査も行いながら、治療の反応を
診て今後のお薬の種類や量を考えています。
そんな愛ちゃんは、とても人懐っこく表情豊かで、いつもしっぽを
ブンブン振って挨拶してくれます

ついついこちらが癒されてしまう程です
いつも、お父さん・お母さんと一緒に来院され、お家での様子などを
私達が問診としてお話をお伺いしています。
とてもよく観察されていて、愛情たっぷりいつも素敵なご家族だなと
感じています

癌の治療というと、かわいそうや辛いといったネガティブな
気持ちになってしまいますが、その中で、愛ちゃんのように
前向きに頑張って闘っているわんちゃん、ねこちゃん
飼い主さんもおられます

愛ちゃんの治療に携わらせていただく中で、私は動物看護師として
何ができるのか?ということを今まで以上に考えるようになりました。
お薬を処方したり、治療の方向性を決めていくのは先生ですが
動物看護師は、会話の中でたとえ些細なことでも飼い主さんが
不安に思われていることや、お家での小さな変化にも気付く
ことができる、話しやすい身近な存在でいることが必要だと
考えています。
一緒に心配し、気持ちを少しでも共有できる存在でいる大切さを
日々感じて、これからも頼りになる動物看護師を目指して
頑張っていきたいと思っています
治療のことだけでなくお家での様子など、相談でも構いません
気軽にお声がけください。
そして愛ちゃん、一緒に頑張ろうね
今回ブログへ快く協力してくださった愛ちゃんご家族に感謝します

募金のご報告 2016.3.23
今年も、待合に設置している2つの募金箱の募金を
下記の各団体にお渡ししました。


 公益社団法人日本動物病院協会(JAHA)
公益社団法人日本動物病院協会(JAHA)
募金額:19,929円
アニマルセラピー事業である、動物介在活動(AAA)
動物介在療法(AAT)、動物介在教育(AAE)に使用されます。
 公益財団法人日本アニマルトラスト
公益財団法人日本アニマルトラスト
募金額: 4,807円 (平成27年11月~平成28年3月)
32,339円 (平成26年12月~平成28年3月累計)
動物たちの保護活動、命の啓蒙活動、保護犬のしつけ・訓練活動
保護動物たちの診療などに使用されます。
募金にご協力いただきありがとうございました

田戸先生がアメリカの学会に参加してきました 2016.3.15
今回は、田戸先生からアメリカ学会
VSSO(Veterinary Society of Surgical Oncology)報告ブログです。

 ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ●
~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● 

腫瘍科の田戸です。
2月に獣医腫瘍外科の会合に参加してきました。
この会合は2年に1度開催される大会で今回の場所は
カリフォルニアのナパバレーです。
ワインで有名な所ですが、主に室内で腫瘍の話ばかりしていました


日本からは酪農学園大学の廉沢先生、北海道大学の細谷先生、
松原動物病院の小山田先生、そしてVRセンターからは田戸の
4人が参加しました

以前、日本に来た腫瘍外科のDr. Rod StrawやDr. Julius Liptak や
Dr. Nick Baconとの再会もあり、新たな先生との出会いもありました。
みんな腫瘍外科の論文や学会でのおなじみの面々です。


Dr.Rod.Strawはコロラド州立大学で獣医腫瘍外科を
発展させたチームの1人で、現在はオーストラリアの
ブリスベンで二次診療施設を運営しています
私自身も以前にその病院に研修に行っており
お世話になった先生です。
左の写真はセミナーで日本に来た時に太秦映画村を
案内しその時に撮影したもので、その日以来の再会でした


Dr.Julius Liptakも多くの教科書や論文に名を連ねている先生です。
左の写真は奈良観光に行った時のものです
偉い先生ですが、すごく気さくで手術の相談などにも真摯に答えてくれます。


パーティーもあり、ワインも飲みましたが勉強がメインでした
会合では骨肉腫、肥満細胞腫、メラノーマ、最小侵襲外科
最新の研究報告が大きなトピックスとして議題に上がり
獣医師だけではなく医師も招いての議論も行われていました。
スマートフォン・タブレットのアプリを使ってカリキュラムが
進行しています
各議題に対しての投票がリアルタイムで集計され
コンセンサスが形成されていく現場に立ち会ってきました。



海外の先生と過ごしていて感じるのは、議論が活発なことです

日本人は議論が苦手と言われていますが、日本の学会でも
ドンドン議論が盛り上がる事を期待してやみません。
今回得られた情報を日々の診療や手術に生かしていく事は
もちろんですが、今後は日本からも世界に向けて情報発信を
行いたいと考えています
いぬのきもち 4月号に富永動物看護師長がコメントしています 2016.3.13
“第3回ペピイアカデミックフェスタ2016″が開催されました 2016.3.3
2/20(土)・21(日)VRセンターに隣接している会場で
『第3回ペピイアカデミックフェスタ2016』が開催されました。

恒例となったペピイアカデミックフェスタは
毎年、VRセンターのスタッフが講師等をさせて
いただいています。
初日は大雨 と悪天候でしたが、2日間で
と悪天候でしたが、2日間で
獣医師160名、動物看護師98名が参加されました
VRセンターの先生方は外科部門を担当しました。
各会場の様子は・・・
 小山先生の眼科学:『眼瞼と角膜の外科』
小山先生の眼科学:『眼瞼と角膜の外科』
 戸次先生の整形外科学:
戸次先生の整形外科学:
『後肢跛行診断:前十字靭帯疾患の診断手順』
『骨折治療戦略:ピンニング』
 田戸先生の腹部外科学:
田戸先生の腹部外科学:
『腹部と骨盤腔の基本的なテクニック』 
 富永動物看護師長が進行役を務めたVNミーティング。
富永動物看護師長が進行役を務めたVNミーティング。
毎月1回、夜に近畿県の動物看護師が中心となって
様々な意見交換を行っているミーティングが
拡大版となり、『動物看護師としてのキャリアアップ』を
テーマに行われました。 
来年もこの時期に開催が予定されています。
VRセンター周辺が動物病院関係の方々で賑やかになった
2日間でした
病気のお話シリーズ vol.10 “動脈管開存症” 2016.2.29
今月の病気のお話ブログは、総合診療科の澤木先生から
『動脈管開存症』に関するお話です
 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
総合診療科の澤木です。
今回は「動脈管開存症」という病気をご紹介させて頂きます。
【動脈管開存症(PDA)とは 】
】 生まれるまで(胎生期)
生まれるまで(胎生期)
赤ちゃんはお母さんのお腹の中にいる間、呼吸をしません。
お母さんの胎盤から酸素を取り込むため、赤ちゃんは出生まで
心臓から肺への血液の流れを殆ど必要としないのです。
よって、無駄な回り道をしない様にするため、大動脈と
肺動脈という太い血管同士をつなぐ「動脈管」という血管が
生まれるまで、どの子にも存在しています。

 生まれた後(出生後)
生まれた後(出生後)
生まれた後、赤ちゃんは肺を使って酸素交換をしなければならなくなり
自分で呼吸し始めると同時に、動脈管はすぐに閉鎖されてしまいます。

生まれた後も動脈管が開いたままの状態なのが、PDAという病気です。
少し細かいお話になってしまいますが、動脈管が開いた状態のままだと
大動脈という太い血管から全身に流れるべき血液が、肺動脈に流れて
しまいます。
結果、肺や心臓(左心房・左心室)に負担が掛かってしまいます

この病気自体は、雌での発生が多く(2~3倍)、チワワ、トイ・プードル
ポメラニアンなどの小型犬に好発すると言われており、猫は比較的
少ないと言われております



【飼い主さんから見て気付く異変(臨床症状)】
はじめは全く症状を示さない子もいますが、心臓の機能が徐々に
低下してくると心臓への負担による咳、呼吸異常(チアノーゼ・
呼吸促迫)、元気がない、運動を嫌がるなどの症状が出てきます。
ワクチン接種や健康診断などで偶然見つかることもあります。
1歳までに70%が左心不全(=心臓の機能低下)を発症すると
言われています。
【診断】
心臓の聴診を含む一般身体検査、レントゲン検査、超音波検査
CT検査などを用いて動脈管が存在することを確認します。
特に、聴診では「連続性雑音」と呼ばれる特徴的な雑音が聴こえます
はじめて獣医さんに連れて行くと、獣医さんが聴診器を当てるのは
この様な生まれつきの心臓病を見つけるためです。
最終的に、超音波検査などを用いて、血液の流れる動脈管を
確認することで、診断されます。
【治療】
動脈管が残った状態である事が、根本的問題であるため、外科治療が
可能であれば、手術が勧められます。
手術方法は、開胸して、閉じていない動脈管を直接閉鎖(結紮)する
方法が取られます。
ただし、症状が進行している場合は、手術可能な時期を逃してしまい
手術適応外となるケースもあります
【さいごに】
PDAは、「今は元気だから…」と、手術を遅らせていると病気が
進行してしまい、手術ができなくなってしまう可能性のある病気です

頑張って手術を乗り越えられれば、他の犬と同様の生活が可能であり
寿命を全うすることができる未来に繋がる手術です

早期発見・早期治療が大事な病気であり、同時に、しっかりとワンちゃんを
診察してくれる「かかりつけの先生」の存在が非常に大切だと思っています。
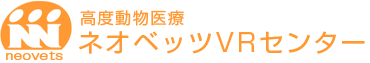
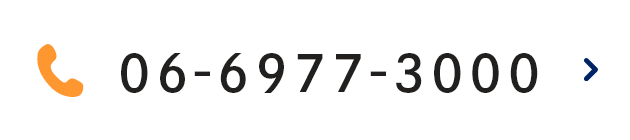



 犬が車に酔う原因は?
犬が車に酔う原因は?